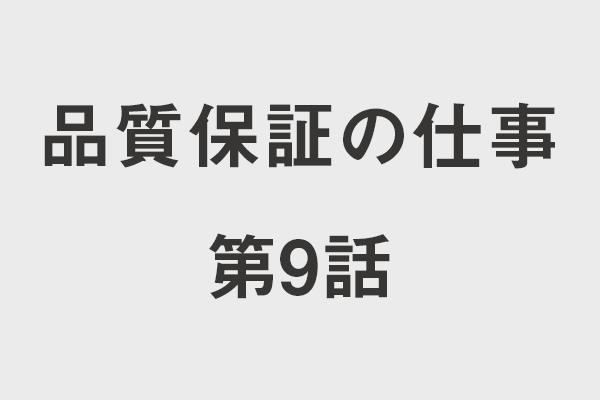「クレーム件数を削減せよ!」
会社により言い方は様々ですが、
品質保証部の業績目標はこれであることが多い。
クレーム関連でしか数値化できるものが無い
と、目標に定めるには最適。
しかし、これがまた適当なものなのだ。
こんなの理不尽だ
必死に頑張る品質保証部。
しかし、業績目標は未達成だ。
クレームに関する費用が増え、予算オーバー。
なぜだ?
故障品の原因分析する人は多いのに、
故障件数が増えた理由を分析する人は少ない。
意外と手間がかかる。
担当外の自分が仕方なく分析した結果、衝撃の事実が判明する。
業績絶好調で出荷数が激増
そらクレーム件数増えるわ
出荷が増えればクレームも増えるのは当然。
初期不良、工事でのミス、勘違い、
出荷数と比例して増えるものです。
こんなん、目標にする数値じゃない
なぜ件数を目標にするのか?
故障などで交換すると、費用がかかります。
その費用削減が品証の目的でもあるので、
「件数削減」が目標となってしまう。
だから、「率」が下がってもダメ。
開発側が「クレーム率」を目標にしているのに、
品証は「クレーム件数」。
もう、ここがメチャクチャな仕事。
どれだけ頑張っても、出荷数次第で目標達成できない。
開発や製造がミスすれば、それで終わり。
だから、目標達成しなくても「仕方ない」と誰も気にしない。
実質的にクレーム件数は個人の評価にほぼ反映されない。
改善数や提案数での評価になる。
結果ではなくプロセスの評価が中心。
逆に、
出荷数が減れば目標達成!バンザイ!
メチャクチャである。
冷静に分析する技術が必要
品質保証部は出荷数の把握が大事です。
これがなかなかデータとして難しい作業になるので、
できる人はごくわずかだった。
なお、いくらパソコンができたり、データベースの知識があってもダメ。
「この部品を使ってる製品の出荷数」
という専門知識が必要になる。
プロじゃないと作れないデータだったりするのだ。
クレーム件数のグラフには必ず出荷数を入れよう。
「ここで出荷数が急増。クレームも急増」
納得の理由です。
ここがないと、「なぜ増えたんだ?分析しろ!」と叱られる。
信頼性解析とか、部品の改訂履歴・寸法調査、いろいろやることはある。
しかし違う、普通に考えてまずは出荷数だ。
だからまぁ、クレーム件数が減った時は出荷数の話はしない。
「品質保証部の努力で件数が減りました!」
これで評価アップ。
部長は喜び、ボーナスアップ。
ここは「違う!」と戦わず、
素直に喜んでおくのが品質保証部の生き方。
馬鹿になることも大事です。
~
しっかり分析し、
「馬鹿らしいわ」と思えるようになったら一人前。
上手く「目標」を利用し、楽しい品証ライフを。
だからまぁ、開発側から馬鹿にされるものですが、
個人プレーが多すぎな職場だった。
組織としての機能が…(略